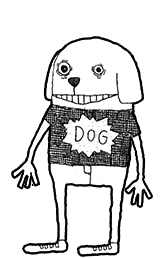知人が亡くなったらしい。
知人と呼ぶのも躊躇われるほど、特に見知っているわけでもないし、ネットでのやりとりを除けば一度しか会って話したことはないんだけど、昔から何かと気になる人だった。ネットで初めて彼を知ったとき、彼は中学生で、そのくせとにかくいい曲を作ってたのでとても驚いたのを憶えている。曲を作りながら絵も描いているところは共感したし、不安や不満の募らせ方、その発散のしかたなどが自分ととてもよく似ていたので、決して他人ではないと思いながら、そしていつか当たり前のようにどんどんすごい人になっていくんだろうなあと思っていた。いったいどんな景色を見ていたんだろう?想像してみたところで他の誰かにわかるわけもないし、その景色から生まれる新しい音楽がもう聴けないというのは寂しいことだけど、そういうことはまあ、起こりうるよな。
そんなことを考えていると、ふと昔のことを思い出した。高校生のころ、僕は自転車で通学していたんだけど、たまに気まぐれでバスを使うことがあった。あまりまじめな学生ではなかったので、授業を抜け出して正午ごろに帰ることもよくあり、平日の真っ昼間で人もまばらな、がらんとしたバス停でバスを待っていたときのこと。少ないながらも待合所で一緒にバスを待ってた人たちが、それぞれの目的地に向かうバスへ乗り込んで行く。だいたいがおじいちゃんやおばあちゃんだったのだけど、その背中を見つめながら、この人とはもう二度と会うこともないかもなあとぼんやり感じていたこと。からっと晴れた昼間に、閑静なバス停でバスを待ってるおじいちゃんやおばあちゃんは、やはりどこか死の匂いがして、だからこそそういうことを感じたのかもしれない。
近いうちにまた会えるという予想のもと誰かと別れて、それが叶わなくなってしまう、という経験をするたびに、目の前にいる人に向けて、この人の顔を見るのはこれが最後かもしれないと強く思うようになっていく。だけど知人の死っていうのは、自分からすると不思議なくらいあっけなく訪れて、そして死んだ当人からするとこれ以上ないくらい必然的なものだったりする。彼が生きつづけることに関与できなかったのを悔いるほど僕は彼のことを知らないし、なんだか厚かましいかなと感じるところもあるけれど、個人的に思うことがあったので、こうして文字に記しておく。良い曲作ってくれてありがとう。